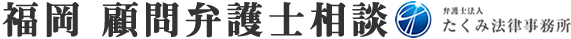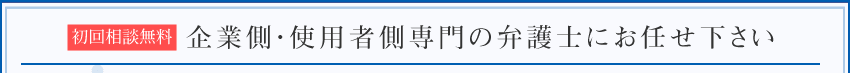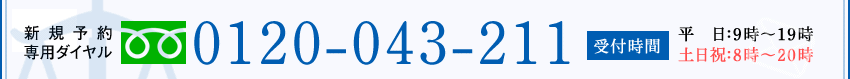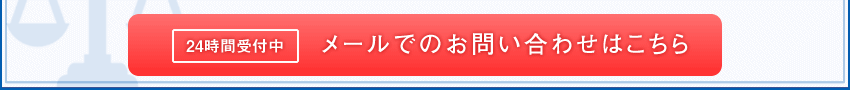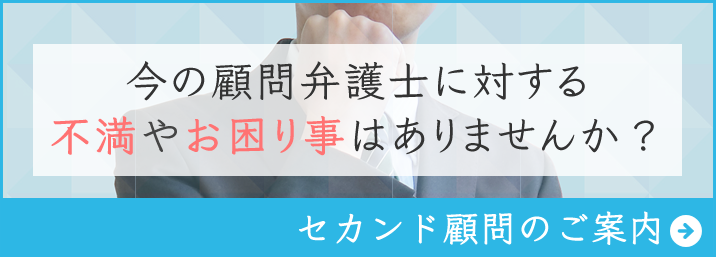導入時の法律問題

今回で成果主義導入・見直しマニュアルは最終回です。
最終回は、これまで説明した成果主義的賃金導入時の法的な注意点について解説します。
これまで歩合給導入のメリット・デメリットについて説明してきましたが、当然のことながら、実際に導入するにあたっては法的な問題点をクリアする必要があります。
歩合給と残業代
「歩合給の場合には残業代を払う必要がない」と誤解されている方もいらっしゃいますが、歩合給の場合でも、残業代を支払う必要があります。
しかも、歩合給を導入した場合の残業代の支払いについては若干複雑です。
通常の残業代の計算式は、
基礎時給×割増率×残業時間
で計算されます。
歩合給(固定給+歩合給)を導入している場合には、まず固定給部分を算出します。
まず、固定給部分の基礎時給を、
月給÷1月平均所定労働時間(170時間程度)
で計算し(月給制の場合)、
固定給部分基礎時給×割増率×残業時間
で固定給部分の残業代を算出します。
そして、次に歩合給部分を算出します。
歩合給部分の基礎時給は、
歩合給÷総労働時間数
で算出します。
※「総労働時間数」で算出する点に注意してください。
そして、
歩合給部分基礎時給×割増率(0.25※)×残業時間
で残業代を算出します。
※割増率が1.25ではなく、0.25(※時間外労働)となることに注意してください。これは、歩合給にはそもそも割増される前の賃金が含まれていると考えられているためです。
歩合給と定額残業代制度
以上のように、少々複雑な計算となりますが、定額残業代制度を採用している企業はさらに複雑な処理が必要となります。
歩合給を採用しつつ定額残業代制度を採用している企業は、賃金制度を見直す必要性が高いでしょう。
定額残業代制度とは、一定程度の残業をしても、残業時間が定額で支払われる賃金制度で、「固定残業代」あるいは「みなし残業手当」と言ったり、「営業手当」という名称で支払われていたりする場合もあります。
定額残業代制度が有効とされるために、現在の裁判例では、
- 基本給と定額残業代が明確に区分されていること(明確区分性)
- 割増賃金の対価という趣旨で支払われていること(対価性)
が必要とされています。
通常、月○○万円を定額残業手当として支払い、その手当は「○○時間相当分」の残業代とするといった形での契約が多いです。
しかしすでに述べた通り、歩合給の場合の残業代は基礎時給額が総労働時間と成果によって異なるため一定ではなく、割増賃金としての対価が具体的にどの程度払われるのかを事前に決定することは困難です。
労働条件の不利益変更

会社と労働者は、合意により労働契約の内容を変更することができます。
しかし、従業員の真の合意が得られているかが問題となることがあります。
たとえば、給与を大幅にカットするといわれて契約条件を変更したとしても、従業員が自らの意思で応じたとは言いきれないことは容易に想像できます。
また会社は、労働者の合意を経ずに就業規則を変更して労働条件を不利益に変更しようと考えるかもしれませんが、これは原則として認められません。
変更の必要性があり、内容の相当性を踏まえ、合理的なものであるときに限って例外的に認められます。
歩合給における歩合率が低下するような変更は「不利益変更」に該当するのは明らかですが、歩合給制度を導入すること自体が契約内容によっては不利益な変更になる場合もありますので、注意が必要です。
現実的には、歩合給を導入する従業員との個別の合意をとることになるでしょう。
その場合、のちに収入が減少した場合になって「一方的に締結を強要された」といわれないよう、具体的に説明する際に合意をするよう心掛ける必要があります。
賃金制度

近年、正規社員と非正規社員との格差の問題である同一労働同一賃金に関する裁判例が立て続けに出ています。
同一労働同一賃金については明確な基準がなく、実務的にも落ち着かない状況が続いています。
また、ジョブ型雇用の導入の議論も始まるなど、個々の会社にあった賃金制度の構築が必要になってきます。
今回は成果主義的賃金制度の概要をお伝えしましたが、賃金制度をはじめとする人事制度戦略はこれからの経営戦略にとって重要さを増してくると思われます。
人事制度戦略でお困りの方は遠慮なくご相談ください。