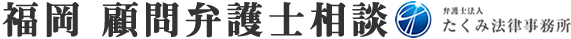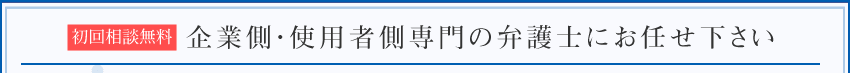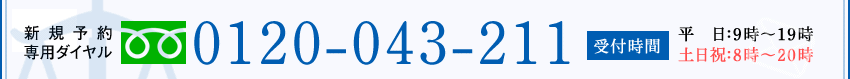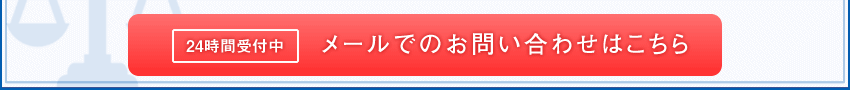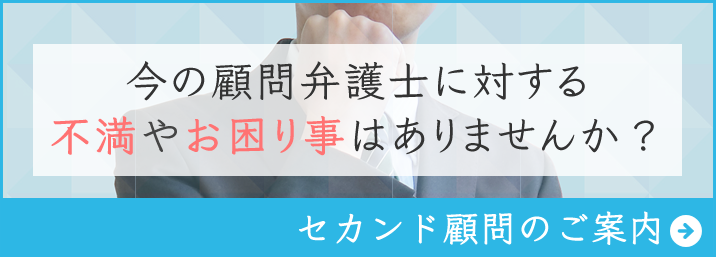求職者が増える時期となり、採用活動を積極的に行っている会社も多いことと思います。
中小企業の採用は、新卒より中途採用が中心となります。
人手不足の昨今、他社で豊富な経験を有する即戦力なら喉から手が出るほど欲しいという会社は少なくないのではないでしょうか。
ところが、履歴書や職務経歴書に記載された経歴を見て期待を込めて採用したものの、実はその人材は前職でトラブルを起こして退社した問題社員だった、ということがありえます。
そのようなリスクを軽減するための手段として、退職証明書の提出を求める方法があります。
中小企業における採用の原則
2-6-2の法則
組織論でよく引用される、「2-6-2の法則」をご存知でしょうか。
組織を構成する人員のうち、自主的で優れた人間が2割、受け身で能力の低い人間が2割おり、残りの6割は平均的な人間であるという法則です。

このうち上位の2割を採用したいと考えるのは自然なことですが、現実には中小企業がそのような人材を採用することは簡単ではありません。
注意しなければいけないのは、むしろ、下の2割を採用してしまうことです。
このような人材は会社に全く貢献しないばかりか、6割の平均的な人材の成長を阻害したり、トラブルメーカーとなるおそれがあります。
つまり中小企業にとっては「採ってはいけない人材を排除すること」が採用の大原則となるのです。
どうやって見極める?
ところが、美辞麗句が並べられた応募書類の情報を元に「採ってはいけない人材」を見抜くことは簡単ではありませんし、トラブルが原因で前職を退社した候補者が面談で退職理由を正直に話してくれるとは考えられません。
退職証明書は、「採ってはいけない人材」を見極めるための有効な手段となります。
退職証明書とは
退職証明書とは、労働者を使用していた事業主が、その労働者を使用していた期間や従事していた業務の種類などの事項を証明する書類をいいます。
退職証明書は労働基準法上「退職時等の証明」と呼ばれており、以下のとおり規定されています(第22条第1項)。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の自由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
ここで列挙されている5つの項目を「法定記載事項」といいます。
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)
退職証明書には、労働者の請求した事項のみを記入することとされており、労働者の請求しない事項は記入することはできません。
たとえば、労働者が法定記載事項のうち「使用期間」と「賃金」について請求を行ったにもかかわらず、「退職の事由」を退職証明書に記入することはできません。
「退職の事由」を確認する
「採ってはいけない人材」の見極めのために必要となる証明事項は、「退職の事由」です。
退職の事由とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇など、労働者が身分を失った事由のことをいいます。
退職の事由が解雇である場合、解雇の理由については具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、該当する就業規則の条項の内容やその条項に該当するに至った事実関係を記入しなければなりません。
退職証明書の請求
労働者本人が請求できる
退職証明書は当事者である労働者だけが請求でき、それ以外の第三者が請求して取得することは当然ながらできません。
したがって、会社は採用候補者に「前職に退職証明書を請求し、弊社に提出してください」と依頼する必要があります。
採用候補者に退職証明書の提出を求めることにためらいを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、履歴書や職務経歴書の内容に相違がないか確認するために退職証明書の提出を求めることは、学歴を確認するために在学証明書や卒業証明書を提出させることと何ら変わりなく、あくまで入社時の事務手続の一環として提出を求めればよいと考えられます。
退職証明書の提出を拒まれたら
前職を円満に退職していない場合には、退職証明書を提出することはおろか、請求すること自体できない可能性が高いです。
したがって、正当な理由なく退職証明書の提出を拒絶する採用候補者がいたら、その方を採用することは避けるのが賢明です。
もっとも、退職証明書に記載された退職理由が「解雇」となっていたからといって従業員に非があることが証明されたわけではありませんので、そのときは退職の経緯を聞き取るようにしましょう。
なお、採用候補者が複数の会社に勤務している場合に直近の勤務先以外に退職証明書の交付を請求することは可能ですが、退職証明書の請求権の時効は退職時から2年とされており、時効を理由に交付を拒まれる場合がありますので注意しましょう(労基法第115条)。
最後に

会社が労務トラブルに直面したときの対処は重要ですが、あらゆる労務問題の端緒は採用にあるということを忘れてはいけません。
採用という「入口」における労務管理術を身に付けることで、将来の労務トラブルを一定数回避することができます。