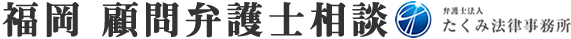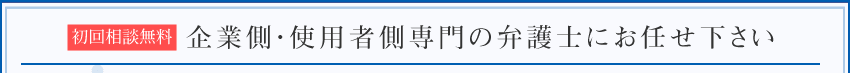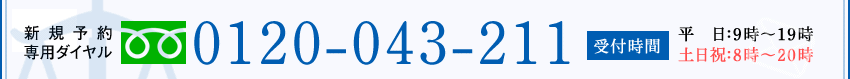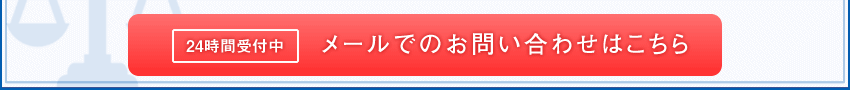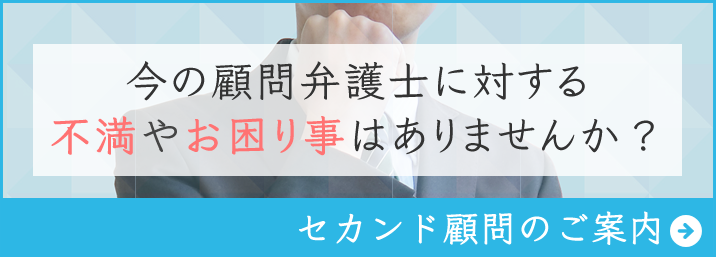歩合の割合は何%まで??

歩合給には、給料の全額を歩合給とするパターン(フルコミッション)と、給料の一部を歩合給とするパターン(固定給+歩合給)の2種類があります。
給料のすべてを歩合とするのか、給料の一部を歩合とするのか、後者の場合には歩合給と固定給の割合をどうするのかという問題があります。
今回は、歩合給を導入する際の歩合給と固定給の割合について考えていきます。
保障給とは
成果主義的賃金のメリットとデメリットを検討するのは当然ですが、ここで考慮しなければならないのは、出来高払い制の「保障給」という考え方です。
法律上、出来高払い制その他の請負制の労働者については、会社は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないとされています(労基法第27条)。
つまり、出来高払い制をとったとして、一切成果を上げなかったとしても、労働時間に応じた一定額の賃金を保証しなければならないという考え方です。
行政の考え方としては、賃金構成から見て固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占めている場合には、本条のいわゆる「請負制」に該当しないとされています(昭22.9.13発基17号、昭63.3.14基発150号)。
ここからすると、歩合給は全体の賃金の中で30%以下とするのが一つの判断基準となるでしょう。
全体賃金の10%程度では歩合給としてのメリットがあまり活かせないともいえます。
計算式の考え方
一般的に歩合給は、
成果 × 歩合率
で計算されます。
歩合給の計算根拠となる「成果」はどのように設定すべきでしょうか。
一般的に会計上「給与」が「販管費」であり、成果主義的賃金が、給与の変動費化を目的とすることからすれば、粗利を成果とするのがもっともシンプルで分かりやすい指標になります。
もっとも、どの業界においても割がいい仕事、悪い仕事というものが存在するもので、取引先との関係性から割の悪い仕事も会社にとっては必要である場合というのは容易に想像できます。
その場合には単純な
粗利 × 歩合率
という計算式ではなく、
粗利 × 取引先との関係を示す係数(ABCランクに応じた数値等) × 歩合率
といったような修正が必要となります。
粗利等のほかには、契約数、目標達成率(もっとも、目標達成率の場合は組織として目標管理制度がしっかりと運用されていることが前提となります。)なども考えられるところです。
歩合率の設定は?

最終的な給与支払額がどの程度になるかについては、事前に試算しておくべきことは当然ですが、適正な人件費率は業種によって大きく異なるため、一概に判断することはできません。
一般的に人件費率とは売上高のうち人件費の割合を指しますが、たとえば、原価の発生する製造業と発生しない労働集約型のサービス業ではまったく異なる数字になるでしょう。
業界ごとの人件費率を参考にすることも多いですが、それでもなかなか正確な数字が出ない場合には、労働分配率が一つの参考になります。
人件費の算定をするときには、利益が出るか・従業員の生活ができるかといった基本的な事項に加え、付加価値がどの程度発生しているかを考慮することが重要です。
付加価値の計算方法は様々なパターンがありますが、一般的には、
人件費 + 純利益 + 減価償却費
などで算出されます。
そして、人件費を付加価値で割った数値を労働分配率といいます。
これは労働者の働きで生み出した価値のうちどの程度人件費に回されるかを示すものです。
近年の標準的な労働分配率は、65%程度です。
ただし、この数字は近年継続的に下がり続けているため、一つの参考基準としてとらえていただければと思います。
歩合率の注意点
歩合率を決定するにあたり、上で説明した人件費率や労働分配率から算出したとしても、一定程度の余裕をとっておく必要があります。
たとえば、保険代理店においては生命保険契約後に保険会社から手数料が支払われますが、その顧客が早期に生命保険契約を解約した場合に、手数料を保険会社に戻さなければなりません(これを「戻入」といいます。)。
これがどの程度想定されるかによって異なりますが、一定程度は余裕を残しプールしたうえで、戻し入れが発生しないことが確定した場合に賞与で支払うなどといった工夫も必要になります。
最後に

歩合給の設計方法についてはここで説明した点以外にも様々な留意点がありますので、設計や見直しを検討されている方は遠慮なくご相談ください。
ここまで歩合給の設計方法についても説明してきましたが、成果主義的賃金制度の一つとして業績連動型賞与を導入している企業も多くあります。
業績連動型賞与においても、上記の設計方法については参考となります。
次回は、最終回として歩合給導入に際する法的な注意点や就業規則等の手続的な側面についてまとめます。