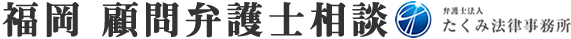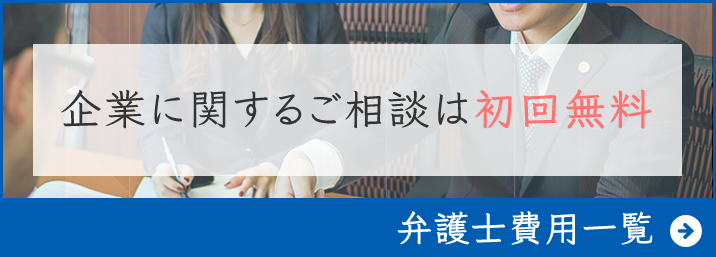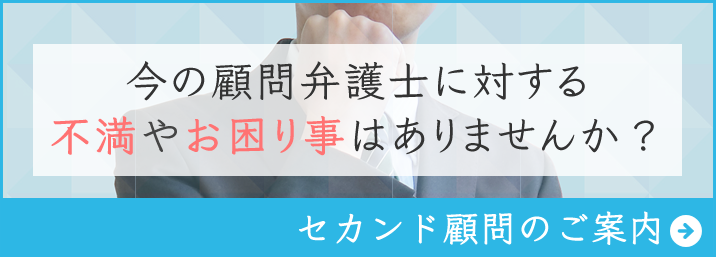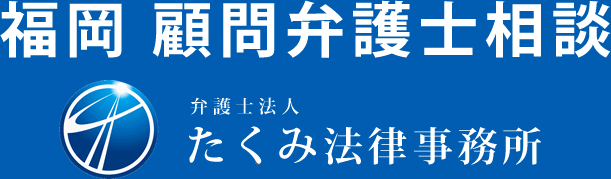退職勧奨とは

退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職(辞職、労働契約の合意解約の承諾など)を促すことをいいます。
それって解雇と何が違うの?と思われるかもしれません。
解雇は、従業員の同意なく、会社から一方的に雇用関係を解消させるもので、会社を辞めさせるか否かのイニシアチブは会社にあります。
退職勧奨は、あくまでも会社から同意を得て退職届を提出してもらい、退職してもらうように促すものです。
したがって、会社を辞めるか否かのイニシアチブは従業員にあるという点が解雇と大きく異なります。
退職勧奨って違法な行為なの?

退職勧奨は、原則として違法ではありません。
退職勧奨は会社がその人事権に基づいて、従業員が自発的に退職の意思を持つように促す行為ですので、従業員の自由な意思を侵害しない限りは、原則として違法とはなりません。
日本では解雇が非常に厳しく制限されていますので、従業員を一方的に解雇した場合、その解雇が不当であるとして、訴訟などに発展するリスクがあります。
しかし、退職勧奨によって合意の上で従業員に退職してもらえれば、解雇のときのようなリスクは発生しません。
そのため、
とはいえ、退職勧奨は、あくまでも従業員の自由な意思に基づくものであることが前提です。
自由な意思を侵害する態様で行われた退職勧奨については、違法なものとして従業員からの慰謝料請求が認められる場合があります。
違法な退職勧奨と判断されるとどうなる?
退職勧奨が違法と判断された場合、労働者が退職の意思表示をしたとしても、後で取り消されてしまう可能性があります。
さらに、従業員から慰謝料請求が認められることになります。
その額は、退職勧奨の態様にもよりますが、場合によっては1000万円以上になる場合もあります。
退職勧奨を行うときに注意するポイント
では、退職勧奨を行うときにはどのような点に注意するべきなのでしょうか
実際の裁判例をもとに解説します。
Point.01しつこい退職勧奨をしない
約4か月もの間に30回以上の退職勧奨を行った事案で、裁判所は、退職勧奨の頻度、面談時間の長さ、退職勧奨の態様が許容できる範囲を超えており、不法行為として、慰謝料の支払いを命じました(全日本空輸事件)。
退職勧奨の際に刑事事件に類似する行為が行われると、違法な退職を強要したと判断され、損害賠償の対象となる可能性があります。
Point.02解雇をほのめかさない
退職勧奨において「自分から退職する意思がないということであれば解雇の手続をすることになる」「どちらを選択するか自分で決めて欲しい」などと説明した事案で、裁判所は、対象となった従業員に解雇事由がないにもかかわらず、会社の説明によって従業員は自ら退職しなければ解雇されると誤信したと認定しました。
裁判所は退職の合意を無効とし、会社に対して、従業員への未払い賃金相当額の支払いを命じました(昭和電線電纜事件)。
Point.03退職に追い込むことを目的として配転や仕事の取り上げをしない
退職勧奨を行っていた時期に会社が従業員に対して嫌がらせをしたり、仕事を取り上げたりした事案で、裁判所は、会社の行為は、明らかに従業員を退職に追い込むためのものであるとして、会社へ慰謝料の支払いを命じました(大和証券事件)。
実際に退職勧奨を行うときの流れは?

このように、退職勧奨はその方法を間違うと会社は多大な損害賠償責任を負うことになりますので、退職勧奨を行うときには十分に慎重になる必要があります。
では、従業員に退職勧奨をするときは具体的にどのように行えばよいのでしょうか。
退職勧奨の方法について法律の規定はなく、その方法は会社の自由ということにはなります。
しかし、すでにでご紹介した事例からもわかるとおり、退職勧奨の方法が度を超えると会社の責任が問われます。
そこで、過去の裁判例を参考にしながら、違法な退職勧奨にならないように十分注意する必要があります。
具体的には、退職勧奨を行うときは次の点に注意しましょう。
- 退職勧奨は必ず面談で行う
- 退職勧奨の内容を書面として残す
- 退職勧奨に対する回答をその場で求めるのではなく、回答期限を設け、検討時間を従業員に与える
- 雇用保険など受給可能な保険も含め、金銭面については丁寧に説明する
- 退職届は必ず提出してもらう
- 社内の人間が複数人退職勧奨に関わる場合、あらかじめ方針や退職勧奨を行う理由などについて全員で情報共有をする
最後に
弁護士にご依頼いただくメリット

退職勧奨は、従業員の人生を大きく変える可能性があるものです。
当事者だけで話をすれば、従業員はどうしても感情的になりがちですし、会社側にとっても、退職させたいという気持ちが先行して違法な退職勧奨を行ってしまう危険があります。
そこで、退職勧奨を検討する際には早めに弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。
第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立は回避できることはもちろんのこと、退職勧奨を行う正当性と金銭的清算など従業員にとってのメリット説明し、従業員が納得して退職できる状況を整えることが可能です。
従業員から違法な退職勧奨であると主張されるなどトラブルに発展することを未然に防ぐこともできます。
退職勧奨がうまくいかなかったときは
退職勧奨は、解雇に伴うリスクを回避する方法としては有効な手段ですが、方法を間違えば、さらに大きなリスクを背負うことになります。
退職勧奨は、一度行うとその従業員と会社との信頼関係は破壊されてしまいますので、退職勧奨を行ったらもう後戻りはできません。
退職勧奨に従業員が応じてもらえない場合、会社としては、その従業員を解雇せざるを得ません。
しかし、解雇をする場合は、不当解雇のリスクがあります。
そこで、退職勧奨を行う場合は、その先の解雇についても適法に解雇できるのかを事前に検討する必要があります。