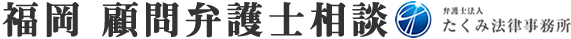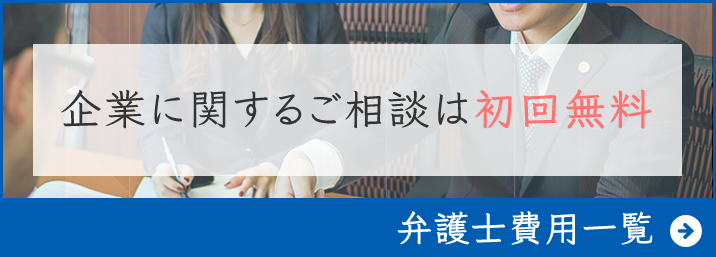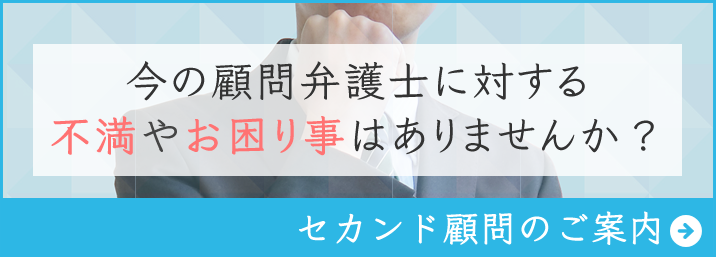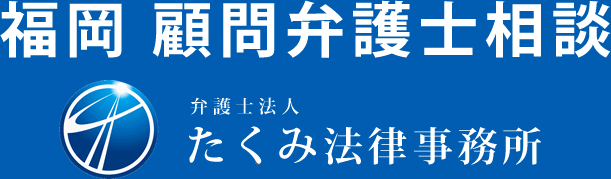「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の基礎知識

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法は、2006年3月31日までの時限立法として制定されていた「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を前身とする法律です。
この法律は、労使間の自主的な取り組みを促進するための努力義務を中心としつつ、多様な働き方に対応した労働時間の設定を実現することを狙いとしています。
なお、この法律でいう「労働時間等」には、労働時間のほか休日及び年次有給休暇その他の休暇が含まれ、「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間(勤務間インターバル)その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
労働時間等設定改善指針
この法律の目的は、「労働時間等設定改善指針」を作成するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別な措置を講ずることにより、労働者の能力を有効に発揮し、労働者の健康で充実した生活の実現と国民生活の健全な発展に資するであるとされています(第1条)。
「労働時間等設定改善指針」は「労働時間等見直しガイドライン」とも呼ばれており、事業主が労働時間等の見直しに向けて取り組むにあたって参考とすべき事項が記載されたもので、厚生労働省のホームページで公開されています(「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針))。
事業主の責務
事業主は、業務の繁閑に応じた労働者の始業・終業の時刻の設定、健康・福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています(第2条1項)。
「終業から始業までの時間」とは、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間の休息の時間、すなわち「勤務間インターバル」を意味します。
これは、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保してワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にするために、十分な勤務間インターバルを確保することを事業主の努力義務として課すものです。
その他の努力義務
また、子の養育や家族の介護を行う労働者に対して休暇の付与その他の必要な措置を講ずることや、単身赴任者など特に配慮を必要とする労働者についてその事情を考慮するよう努めることが求められています。
さらに、取引を行う他の事業主に対する努力義務も定められています。
具体的には、著しく短い期間の設定や発注の内容の頻繁な変更を行ったり、労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないなど、取引上必要な配慮をするよう努めなければならないとされています。
労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
事業主は、労働時間の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならないとされています(第6条)。
具体的には、事業主を代表するものと労働者を代表する者を構成員とする委員会を設置して、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べられるようにするなどの措置が挙げられています。
このを「労働時間等設定改善委員会」といいます。
労働基準法の適用の特例
労働時間等設定改善委員会を設置した事業主は、次の制度を導入する際に特例が認められ、労働時間等設定改善委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議を労働基準法で定められた労使協定に代えることができます。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制。(対象期間を1か月以上の期間に区分する場合の特例にかかる「同意」を含む)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 休憩の一斉付与の適用除外
- 時間外及び休日労働
- 代替休暇
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 時間単位年休
- 年次有給休暇の計画的付与
また、本来労働基準法では行政官庁への届出が必要とされている次のものについては届出を要しないとされています。
- 1か月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制(清算期間1か月超)
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 「パートやアルバイトには有休を付与しなくていい」は間違いです
- 「不当解雇」と言われたら?会社を守る方法を使用者側専門の弁護士が解説
- 「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の基礎知識
- 「賃金の支払の確保等に関する法律(賃金支払確保法・賃確法)」の基礎知識
- ハラスメント(パワハラ、セクハラ)のリスクを使用者側専門の弁護士が解説
- ハラスメントが起きたときに会社がとるべき対応を使用者側専門の弁護士が解説
- ハラスメントを防ぐ3つの方法を使用者側専門の弁護士が解説
- フレックスタイムとの違いは?裁量労働制のポイント
- みなし労働時間制の基礎知識
- 使用者側専門の弁護士が解説|従業員に対する所持品検査が適法とされるのはどんなとき?
- 出張の移動時間は労働時間になる?使用者側の立場から解説!
- 労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない労働者とは?
- 労働時間との違いは?休憩時間の基本ルールと「休憩の3原則」
- 労働者ってどんな人?労務管理の基本となる「労働者性」について解説
- 労務リスクはM&Aリスク?労務問題とM&Aの関係
- 問題社員への対応を使用者側専門の弁護士が解説
- 団体交渉を申立てられたときの対応を使用者側専門の弁護士が解説
- 契約社員を雇い止めするときの注意点を使用者側専門の弁護士が解説
- 学歴詐称や職歴詐称などの経歴詐称を理由に従業員を懲戒解雇できる?
- 就業規則の不利益変更の注意点を使用者側専門の弁護士が解説
- 就業規則の作成や変更が必要になるのはどんなとき?
- 就業規則を周知していないと懲戒処分が無効に?
- 弁護士が解説!労務リスクから企業を守る「3つのお守り」とは?
- 待機時間は労働時間になる?
- 従業員が横領したら返還請求や解雇はできる?給与からの天引きは?
- 従業員の解雇や退職勧奨でお困りの際は使用者側専門のたくみ法律事務所へ
- 心理的負荷による精神障害の認定基準にパワーハラスメントに係る出来事が明示されました
- 意外と知らない?給料の支払い方法の5つの原則を使用者側専門の弁護士が解説
- 懲役・罰金など労働基準法(労基法)違反の罰則について徹底解説
- 懲戒処分を社内で公開することは名誉棄損やプライバシー侵害になる?
- 新型コロナウイルスの感染拡大で衛生委員会を延期したりテレビ会議で開催できる?
- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い時差出勤を導入する方法
- 新型コロナウイルスの感染拡大を理由に内定を取り消しできる?
- 新型コロナウイルス流行で注目されるテレワークの法的問題は?
- 普通解雇と懲戒解雇の違いとは?使用者側専門の弁護士が解説
- 未払い残業代を請求されたら確認するべき5つのポイント
- 横領など従業員の不祥事が発覚したときの会社の対応
- 歓送迎会後の交通事故で企業にも責任が生じる?
- 社員が50名を越えたら|経営者が知っておくべき「産業医」の基礎知識
- 福岡で労働問題についてお困りのときはたくみ法律事務所の弁護士に相談
- 福岡で労働審判を起こされたらたくみ法律事務所の弁護士に相談
- 福岡で問題社員についてお困りのときはたくみ法律事務所の弁護士に相談
- 福岡県で労働審判を申し立てられたら弁護士に相談
- 競業避止義務の問題を使用者側専門の弁護士が解説
- 解雇期間中の賃金の支払いについて弁護士が解説
- 試用期間の基礎知識|試用期間は自由に解雇できると思っていませんか?
- 賃金や労働時間の端数処理は労基法違反?認められるのはどんなとき?
- 資格取得費用の返還合意は有効?使用者側専門弁護士が解説
- 退職勧奨のポイントを使用者側専門の弁護士が解説
- 雇用契約書(正社員)の作成のポイントを使用者側専門の弁護士が解説
- 従業員を解雇する前に弁護士にご相談を―安易な解雇は危険です
- 就業規則の作成と届出のポイントを使用者側専門の弁護士が解説
- 従業員のメンタルヘルスの問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください
- 残業代対策として固定残業代制を導入するときのポイント
- 労働審判を申し立てられた会社がすぐに弁護士に相談した方がよい理由
- 労働問題の弁護士費用